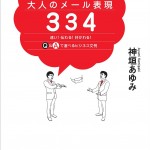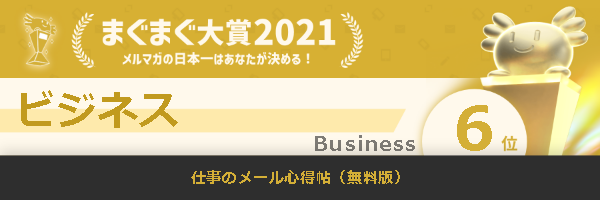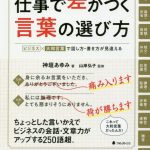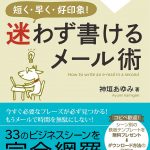読みは同じでも意味が異なる言葉があります
(同音異義語)。
先週取り上げた「張る」と「貼る」に関連して
今回は「添付」と「貼付」の違いについてです。
「添付」と「貼付」の使い分け
できていますか?
「添付」は、文字通り、付け添えること。
例)添付ファイル、領収書を添付する
一方、「貼付」は、
のりなどで貼り付けることを指します。
例)封筒に切手を貼付する、写真貼付欄
「貼付」の本来の読みは「ちょうふ」で、
その慣用読みが「てんぷ」です。
「貼付」を「ちょうふ」と読み、
「添付」と区別している人も
いるかもしれません。
「添付」と「貼付」を調べていて
こんな一文を見つけました。
「領収書等はA4用紙にコピーまたは貼付して
添付してください」
この文では、
領収書等をA4用紙にコピーするか、
のりで貼り付けてから、
書類に付け添えてください
という意味でしょう。
「貼る」と「張る」、「添付」と「貼付」
といった同音異義語は文字を入力するとき、
迷ったり、間違って使ったりすることが
あります。
入力間違いを避けるためにも
それぞれの意味を知っておきましょう。
意味の違いを調べるときに役立つのがこちら
仕事実績、著書、お問い合わせは・・・
神垣あゆみ企画室